現時点では
どちらも主に炭素と水素からなる有機化合物
非極性分子構造を持つ
疎水性(水をはじく)と親油性(油に馴染む)の性質を共有
「似たものは似たものに溶ける」原則に従って互いに強く相互作用
この化学的類似性が、プラスチック容器から油汚れが落ちにくい現象の根本的な理由。両者の分子レベルでの親和性により、油はプラスチック表面の微細な隙間に入り込み、水だけでは容易に除去できなくなる。
というのがもっともらしい理由として納得できた。
本当にそうなのかはわからないから今度理学部の友人に聞いてみよう。
色々情報を探してみると石油と油だからという記述が見つかった。。。
それはかなり違和感がある。
そんなこといったら水(H2O)は水素(H)を含んでいるから酸素と結びついて激しい燃焼反応を起こすといっても通ってしまうんじゃないか?
簡単に物事を伝えるために例え話をするならよいけどもっともらしい話として語ってしまうのは作り話なのではないだろうか?
高校のときの化学の授業で「洗剤は水といっしょに使うことできちんと油汚れを落とせる」、ということを先生がおっしゃっていたのを思い出した。界面活性剤とかミセルの話だったと思うけどその時は納得していたけど最近まで忘れていた。
「洗剤はそのまま汚れにかけたほうが汚れが落ちそう」ということを最近まで思っていたのが恥ずかしい。
思い込みは気をつけなくては。
なにか間違えていることがあれば教えてください。よろしくお願いします。

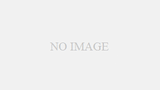
コメント